夜勤と子育ての両立に悩む共働き家庭のみなさん!いつもお疲れ様です。
我が家も夜勤妻×共働きパパとして日々頑張っております!
工夫次第で充実した家族時間を確保できるんです。
この記事では、実際に両立にしている我が家の経験や他の家庭のパターンをもとに、
- スケジュール管理
- 家事と育児の役割分担
- サポートの構築
- 健康と睡眠の管理
4つの工夫を紹介させていただきます。
夜勤による不規則な生活リズムがあっても、夫婦が互いに思いやり、協力し合うことで、子どもの成長を見守りながら仕事も続けていけます。完璧を目指さず、あなたの家族に合った両立スタイルを一緒に考えてみませんか?
✅ スケジュール見える化が必須 – アプリ・カレンダーでシフト共有、緊急調整も積極的に
✅ 状況に応じた役割分担 – 夜勤日・夜勤明けで完全に分担変更、公平より無理のない分担
✅ サポート構築を躊躇しない – 祖父母・ファミサポ・公的サービスは遠慮なく活用
✅ 夜勤明けは睡眠最優先 – 遮光カーテン・耳栓で環境整備、家族ルール徹底
✅ 月1回の家族会議 – シフトに合わせて役割を事前決定、見えないと忘れるを防止
夜勤と子育ての両立は本当に可能なのか?共働き家庭の実態

「今日も夜勤。またか…」
「このままで本当に子育てと両立できるのかな?」
そんな不安、感じていませんか?少なくとも私たちの家庭は感じてました。医療従事者、工場勤務、警備員などなど。夜勤は様々な職種で避けられない現実ですよね。
でも、安心してください。私たちも夜勤と子育ての両立に非常に悩んだ経験があります。そこで分かったのは、適切な工夫と家族の協力があれば、十分に両立できます。
職種別の夜勤の実態と課題
職種によって夜勤の形も悩みも違いますよね。我が家で言うと、家の妻は看護師さんをしております。2〜3交代制で「今日は日勤、明日は夜勤、夜勤明け」といった不規則なシフトです。
工場勤務の方は「ずっと夜勤固定」というケースもありますよね。
妻に聞くのですが、「深夜まで及ぶ長時間勤務は体力的にきつい」とのことです。そりゃそうですよね。
職種ごとに課題は違います。看護師さんは急な呼び出しへの対応、工場勤務の方は長期間の生活リズム逆転による体調管理など。でも、それぞれに対応策はありますよ。
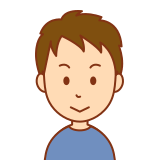
我が家も絶賛もがき中です!
子どもの年齢別に見る夜勤との両立のポイント
子どもの年齢によっても悩みは変わっていきます。
0歳児の時は、「夜中の授乳と夜勤明けの睡眠欲求が重なって本当に大変…」と。この時期はパートナーのサポートが特に重要です。
幼児期になると、「保育園のお迎えに間に合わない」、「参観日に行けなかった」という葛藤も。我が家も絶賛苦労中です。
そして、学童期には宿題のチェックや学校行事への参加など、また違った課題が出てきます。
夜勤明けでヘトヘトな妻はやっぱり寝てしまいます。そんな中、パパは不規則な勤務ではないので「パパ、遊ぼう!」と子供が元気に飛びついてくることが多々あります。
我が家では疲れていても、少しの時間でも質の高い関わりを持つことを意識した上で、子供とかかわっております。
コミュニケーションをとることで、子どもの安心感につながります。
夜勤と子育ての両立!共働き家庭でやっておくべき4つの工夫
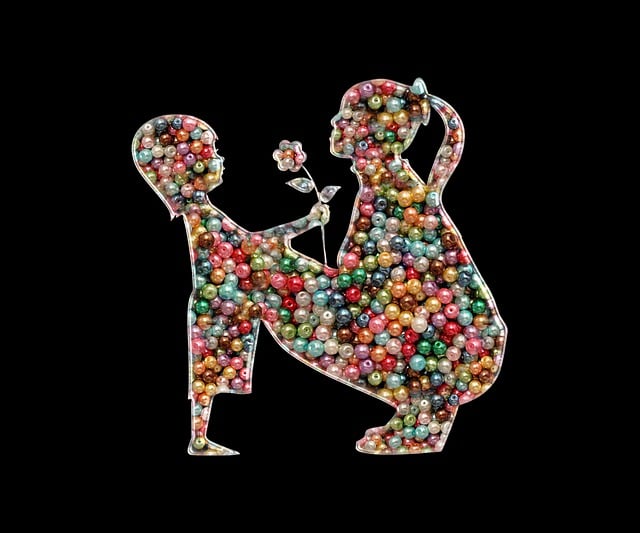
具体的にどうすれば両立できるのか、実践的な工夫を紹介しますね。これから紹介する4つの方法は、我が家では実際に効果を上げているものです。
いきなり全部を取り入れようとすると大変なので、「これなら今日からできそう!」というものから少しずつ試してみてくださいね。
スケジュール管理の方法
夜勤がある家庭で一番大切なのは、先の見通しを立てることです。「明日、誰が子どものお迎えに行くんだっけ?」というバタバタした状況は避けたいですよね。
私の家ではアプリとカレンダーを使って、シフト表を見える化しております。
- 夜勤なのか
- 夜勤明けなのか
- 日勤なのか
- 休みなのか
一目でどんな状態になっているのかを分かるようにしています。
アプリを使う場合は、家族共有設定にしておけば、出先でも確認できて便利ですよ。
夫婦のシフト調整テクニック
「お互いの予定を把握するだけじゃ足りない!」そう感じたことありませんか?実は積極的な調整が必要なんです。色々と歪みがでてきますからね。
看護師として働く妻は、どうしても調整しないと難しいといった場合は病棟の師長さんに相談してもらってます。「子育て中だから無理」と諦める前に、職場に相談してみる価値はあります。昨今の情勢もありますが、理解を示してくれます。
また、カレンダーに子どもの運動会や健診など、絶対に親が参加すべき日を赤丸でマークして、その日は絶対に休みを取る、というルールを決めている家庭もあります。
大切な日を見逃さないためのちょっとした工夫です。
家事と育児の明確な役割分担のコツ
「今日は誰が何をするの?」があいまいだと、結局一人に負担が集中してしまいます。これ本当に家庭として良くない方向にいっちゃいます。
我が家では、「夜勤の日」「夜勤明け」で役割分担がガラッと変わっています。ワンオペになっちゃうから当たり前なんですけどね。
- 子供のご飯
- 入浴
- 寝かしつけ
- その他雑務
夜勤明けの日も妻を配慮して基本全部引き受ける。無理なものは無理ですからね。
長い目で見ると家事という役割を公平にすることより「その時の状況に応じた無理のない分担」が長続きのコツなんです。「疲れているときは頼っていいんだよ」という安心感が夫婦間で共有できれば、心の余裕も生まれますよ。これ本当に重要です。
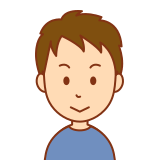
お恥ずかしい話ですが、
しばらく料理などを完璧にこなそうとして共倒れになりそうな時期がありました。。
今では時短家電や冷凍の作り置き、たまには出前も躊躇なく活用しています。
完璧を求めすぎないことが本当に大切です!
サポートの構築と活用法
「二人だけで何とかしなきゃ」と思っていませんか?それ、実はとても大変なことなんです。
子育ては一人や夫婦だけでするものではありません。頼れる人は遠慮なく頼りましょう。近くに祖父母がいる方は本当にラッキー。でも「毎回お願いするのは申し訳ない」という気持ちも分かります。
もし助けを求められるのであれば、月に1回とか2回だけでもいいので、定期的に祖父母に来てもらって助けを求めるのはアリだと思います。回数を決めることで、お互いに負担にならない関係が続けられればいいですよね。
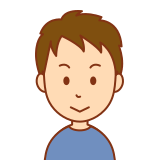
我が家では頼れない状態ですが、
もし頼れるなら頼ったほうがいいですよ!
親族の助けが得られない場合は、ファミリーサポートセンターなどの公的サービスも検討してみてください。最初は「知らない人に子どもを預けるなんて…」と不安もあるかもしれませんが、利用してみると「こんなサービスがあって良かった」と感じます。
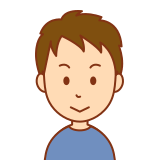
地域の子供センターとかいいですよ。
みんな仲間感が出て、すごい安心します。(笑)
健康と睡眠の管理テクニック
夜勤をしていると、どうしても睡眠不足になりがちですよね。でも、それが積み重なると家族みんなが不機嫌になってしまいます。
わが家では「夜勤明けの日は夕食までは基本起こさない」というルールがあります。
子どもたちにも「ママが元気になるには、しっかり寝てもらうことが大事なんだよ」と教えています。
寝室環境も大切です。
- 遮光カーテン
- 耳栓
- 睡眠用アイマスク
- その他睡眠グッズ
少し贅沢かもしれませんが、夜勤をしている方への「家族からの投資」だと思えば、決して無駄ではありません。
睡眠だけではなく、食事や運動にも気を配りましょう。不規則な生活だからこそ、意識的に体調管理することが大切です。「家族のために」と無理を重ねると、いつか必ず限界がきます。自分の健康を守ることは、家族を守ることにもつながるんですよ。
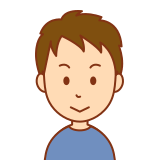
無理して身体壊したら意味ないです!
夜勤と子育ての両立に成功している共働き家庭の事例
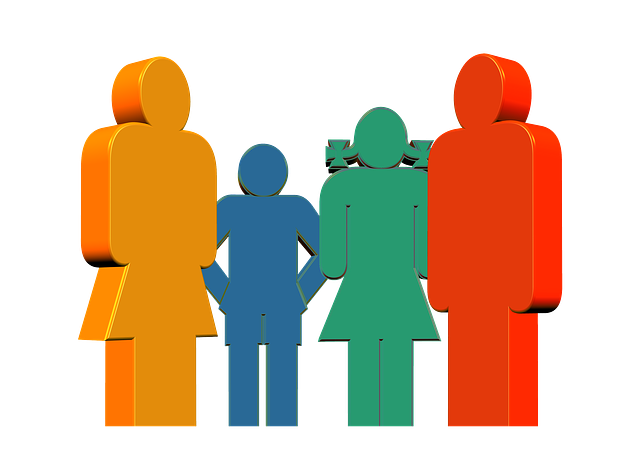
実際に夜勤と子育てを両立させている家庭からヒントをもらいましょう。「他の家庭はどうしているんだろう?」と気になりますよね。
看護師と会社員の夫婦の工夫とルール
我が家の例を紹介しますね。妻は看護師で二交代制の夜勤、私は一般企業の会社員です。
私たちの工夫している点の1点目は、毎月家族会議を開いていることです。
その月のシフトに合わせて「誰が何をするか」を決めています。
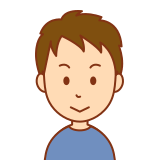
いずれは子供にも参加してもらおうと思ってます
2点目は、見える化です。
カレンダーのみだけではなく、スマホでも予定の共有、何を買うべきか否かなど家庭に関わることは見えるように共有しています。「見えないと忘れる」というシンプルな原則が私たちの生活を支えています。
3点目は、夜勤明けの日は妻の睡眠を最優先に。
4点目は、お休みの日のご飯は基本的にパパがすべて作るです。
これ結構いいです。私もはじめは大変だったのですが、妻は子供に関わることに集中ができ、パパはその他家事全般をする。これをずっと続けてることでお互い感謝の心が芽生えています。
別の記事でまとめていますので、こちらも是非確認してみてください。
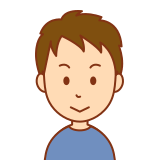
ギブアンドテイクの関係が大事です。
お互いを思いやる気持ちを忘れると破綻しちゃうので注意です!
夜勤と子育ての両立で活用できる支援制度
知っているようで意外と知らない、夜勤家庭向けの支援制度。活用しない手はありませんよ。
自治体によっては24時間保育や病児保育、子どもの一時預かりサービスなど、夜勤家庭を支えるサービスが充実しています。また、「ファミリーフレンドリー企業」と呼ばれる、子育て中の従業員に配慮した勤務体制を整えている会社もあります。こういった企業に転職するのもアリです。
子どもが小さいうちは夜勤免除の制度を利用し、子どもが小学校に上がってから夜勤に戻る、といったこともできます。会社の理解さえあれば、ライフステージに合わせた働き方の調整をすることが可能です。
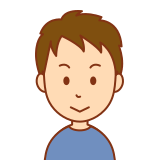
家庭に合わせた働き方、見つけていきたいですね
おわりに
最後にお伝えしたいのは、夜勤と子育ての両立は決して楽ではありません。これは私が現在進行形で実体験として断言できます。本当に色々なイベントが発生し、大変なことだらけです。
工夫次第で充実した家庭生活を送ることはできるということ。一度にすべてを完璧にしようとせず、家族の健康と幸福を第一に、少しずつ自分たち家族に合ったスタイルを見つけていきましょうね。
あなたなりの両立方法が見つかる日は、きっとそう遠くないはずです。
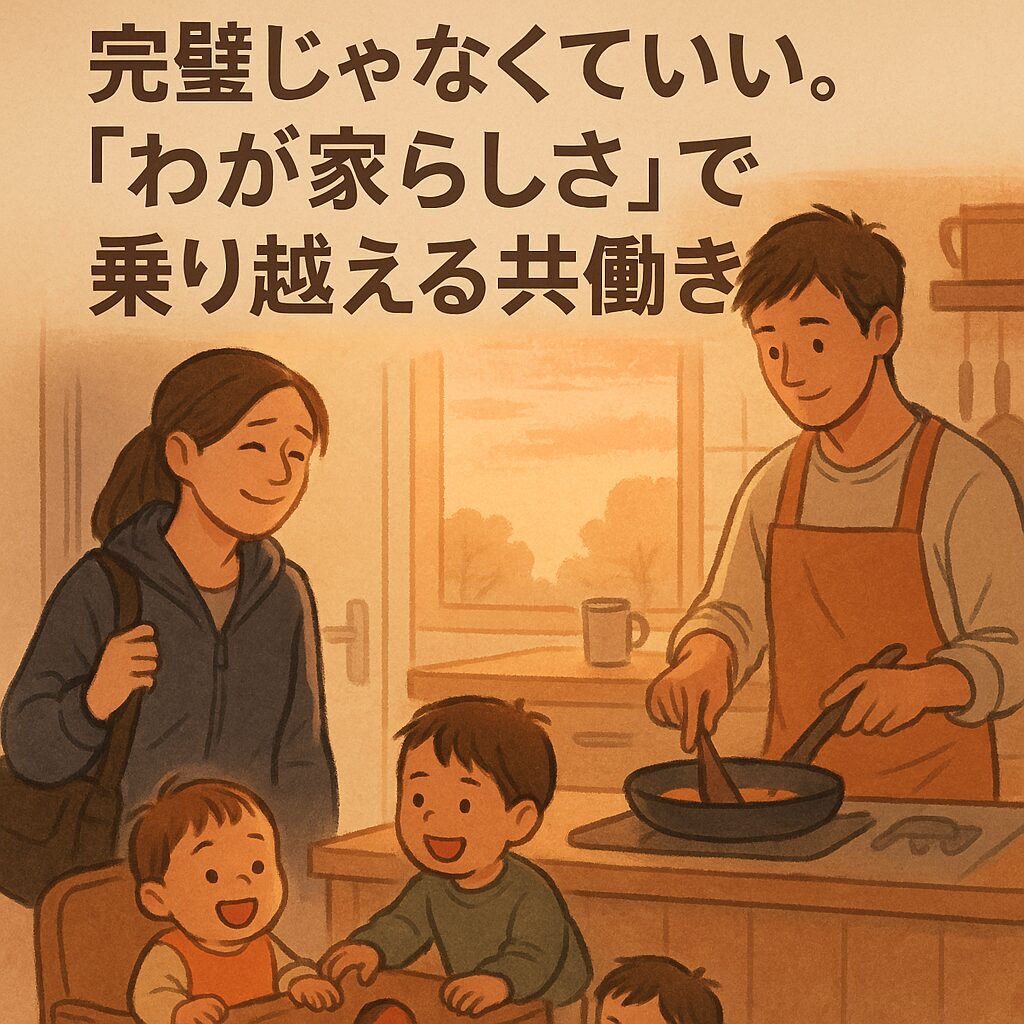

コメント